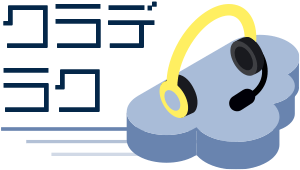コールセンターのBCP対策とは
頻発する自然災害、新たな感染症の脅威、そして予測不能なシステム障害。現代の企業経営において、事業継続計画(BCP)の策定はもはや「他人事」ではありません。特に、顧客との接点を一手に担うコールセンターが機能不全に陥ることは、企業の信頼と収益に致命的なダメージを与えかねません。本記事では、部長クラス以上の責任者の方が知るべき、コールセンターにおけるBCP対策の要点と、その切り札となるシステム活用法を解説します。
BCPとは何か?コールセンターにおける意味
BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)とは、災害や事故などの緊急事態が発生した際に、企業が損害を最小限に抑え、中核となる事業を継続・早期復旧させるための方針や手順をまとめた計画のことです。特にコールセンターにおけるBCPは、単なる社内業務の継続に留まりません。それは、社会インフラとしての顧客窓口を維持し、顧客の不安を取り除き、企業の社会的責任を果たすという、極めて重要な意味を持ちます。
なぜコールセンターにBCPが必要なのか
コールセンターは、多くの企業にとって顧客と直接対話する唯一の窓口です。このライフラインが寸断されれば、製品の注文が止まり、サポートを求める顧客は路頭に迷い、不安はクレームへと発展します。BCPの欠如は、機会損失、顧客満足度の低下、そしてブランド信用の失墜に直結します。顧客接点を維持し、緊急時においても「いつも通り」の安心感を顧客に提供し続けることこそ、コールセンターにBCPが不可欠である最大の理由です。
想定されるリスクと被害例
コールセンターの機能を停止させるリスクは、私たちの身近に潜んでいます。
- 自然災害 地震、台風、豪雨、豪雪によるオフィスへの出社不能や、停電・通信網の遮断。
- 感染症パンデミック 従業員の出社制限や、多数の罹患者発生による人員不足。
- システム障害 サーバーダウンやネットワーク障害による業務停止。
- セキュリティ事故 サイバー攻撃によるシステム停止や情報漏洩。
これらの事態が発生すれば、電話が一切繋がらない、顧客情報にアクセスできないといった直接的な被害に加え、対応の遅れがSNSで拡散され、二次的なブランド毀損を招く恐れもあります。
日本のコールセンターが特に直面する課題
日本のコールセンターは、その構造上、特有の脆弱性を抱えています。多くのセンターが交通の便が良い大都市圏のオフィスビルに集中しているため、首都直下型地震などの広域災害が発生した場合、複数の拠点が同時に機能不全に陥るリスクがあります。また、長らく「出社」を前提とした運営体制が主流であったため、在宅勤務へのシフトが遅れ、パンデミックのような事態に迅速に対応できないケースも少なくありませんでした。
BCP策定の基本ステップ(4STEP)
BCPは、単なる文書作成に留まりません。机上の空論で終わらせないためには、以下の4つのステップに沿って、実践的な計画を練り上げましょう。
1. 業務・機能の優先順位を特定
緊急時に全ての業務を100%継続することは不可能です。受注、緊急サポート、一般問い合わせなど、事業継続の観点で最も優先すべき業務は何かを特定し、限られたリソースをそこに集中させる判断基準を設けます。
2. 運用体制・ルールの統一
緊急時の指揮命令系統、オペレーターへの連絡網、顧客へのアナウンス方法など、誰が・何を・どのように行うかを具体的に定めたマニュアルを策定します。判断に迷う時間をなくし、迅速な初動を可能にすることが目的です。
3. システム環境・勤務環境の整備
BCPの実効性は、それを支える環境に依存します。後述する在宅勤務が可能なシステム環境の整備や、代替拠点の確保など、物理的・技術的な準備を進めます。
4. 定期的な訓練・シミュレーション実施
策定した計画は「絵に描いた餅」では意味がありません。定期的に訓練やシミュレーションを行い、計画の有効性を検証し、課題を洗い出して改善を繰り返すPDCAサイクルを回すことが不可欠です。
コールセンターBCPの具体的な対策例
BCPの実効性を高めるためには、「拠点」「人」「プロセス」といった複数の観点から対策を組み合わせることが重要です。ここでは、代表的な対策例をいくつか紹介します。
- 在宅コールセンターの構築 オペレーターが自宅から業務を行える体制を整備します。これにより、出社困難な状況でも業務を継続できます。
- ノンボイス化の推進 電話以外のチャネル(チャット、メール、SNS)での対応を強化します。呼量が集中する緊急時において、問い合わせチャネルを分散させる効果があります。
- セルフサービス・FAQの活用 顧客が自己解決できるFAQサイトやチャットボットを充実させることで、入電数そのものを抑制します。
- マルチ拠点化・外部委託 複数の地域に拠点を分散させたり、一部の業務を外部委託したりすることで、一つの拠点が被災した際のリスクを分散します。
BCP対策に役立つクラウド型コンタクトセンターシステム
前述の対策、特に在宅勤務やノンボイス化を強力に推進するのが、クラウド型コンタクトセンターシステムです。このシステムは、BCP対策において絶大な効果を発揮します。
- 場所を選ばない業務継続 インターネット環境さえあれば、オペレーターは自宅や代替拠点から即座に業務を再開できます。
- 物理的リスクからの解放 自社でサーバーなどの機器を持つ必要がないため、オフィスの被災による設備破損のリスクがありません。
- 柔軟な管理機能 管理者は遠隔地からでも、オペレーターの稼働状況をリアルタイムで監視し、着信のルーティングを柔軟に変更できます。
- 迅速な導入と拡張性 新たな拠点の追加や、チャットなどの新チャネルの導入も、迅速かつ低コストで行えます。
WFM(ワークフォースマネジメント)機能の有効性
緊急時においては、オペレーターの稼働可能人数も流動的になります。このような状況で役立つのがWFM(ワークフォースマネジメント)機能です。誰が・いつ稼働できるかをリアルタイムで可視化し、限られた人員でサービスレベルを最大限に維持するための最適なシフトを自動で再編成します。勘や経験に頼らない、データに基づいた人員配置が、混乱期の安定したセンター運営を支えます。
BCP対策を実現する上での5つのチェックポイント
BCPを策定・導入した後は、その実効性を定期的に点検する必要があります。ここでは、最低限確認すべき5つのチェックポイントを挙げます。。
- 拠点・設備の状況把握 自社拠点のハザードマップ上のリスクや、インフラ(電源・通信)の二重化はされているか。
- 基本ルール・マニュアルの策定 緊急時の連絡体制や、オペレーターの行動基準は明確に文書化されているか。
- 従業員のサポート・ケア 緊急時における従業員の安全確保や、メンタルヘルスケアの体制は整っているか。
- リモートワーク体制の構築 在宅勤務に必要なPC・通信環境の整備や、勤怠管理・教育のルールは確立されているか。
- 情報セキュリティとコンプライアンス 在宅環境でもオフィスと同等のセキュリティを担保する仕組み(VPN、アクセス制限など)はあるか。
成功事例・失敗事例から学ぶ
ある地方の企業は、クラウド型コンタクトセンターシステムを導入し、普段からオペレーターの2割が在宅勤務する体制を構築していました。地域を襲った豪雨災害でオフィスへの通勤が寸断された際、翌日には全オペレーターを在宅勤務へ切り替え、問い合わせ業務をほぼ通常通り継続。顧客からの信頼を高めました。 一方、別の企業はBCPを策定せず、オンプレミス型システムに依存していました。大規模なシステム障害が発生した際、復旧に72時間を要し、その間すべての顧客対応が停止。ビジネスに甚大な被害をもたらしました。
BCP対策は企業の未来を守る「必須投資」
これからのコールセンター運営において、BCP対策は特別な取り組みではなく、標準装備すべき必須要件です。そして、その実効性を担保する最も強力な基盤が、クラウド型コンタクトセンターシステムであることは間違いありません。これからシステムを選定する際は、平常時の業務効率だけでなく、「緊急時に、いかに事業と顧客を守れるか」というBCPの視点を、最重要の評価軸の一つとして加えるべきです。それが、未来の不確実性に対する最も賢明な投資と言えるでしょう。
業界特有の課題を
解決できる製品を選ぼう
解決できる製品を選ぼう
コールセンタークラウドシステムが活用されている業界は幅広いため、製品選びを成功させるには、自社の業界に合った機能を備えている製品を見つけることが大切です。
当サイトでは、導入する業界別におすすめのコールセンタークラウドシステムをピックアップ。業界特有の課題をどのように解決できるのか、理由と併せて紹介しています。自社の業界にマッチする製品を見つけたい方は、ぜひチェックしてみてください。
業種別
クラウド型コールセンターシステム3選
クラウド型コールセンターシステム3選
コールセンターの運用を適正化し、事業成長を加速させられるクラウド型システム。業種・業界ごとの課題に応じて導入し、変化に強いコールセンターを構築しましょう。
金融・保険業界
Genesys Cloud CX

引用元:Genesys Cloud CX公式HP
(https://www.genesys.com/ja-jp)
(https://www.genesys.com/ja-jp)
- 強固なセキュリティ対策で
重要な顧客情報を守る - 複数の防御対策を掛け合わせ、企業ごとに固有の暗号化キーも採用。PCI DSS、GDPR、ISO 27001等、国際的な金融セキュリティ基準に準拠しています。
- セキュリティとAI活用で
顧客対応・監査の負担を削減 - AIが顧客情報を分析して適切なオペレーターをアサインし、初回解決率を向上。個別対応が重要なローン・信託相談の効率化に寄与します。
金融・保険業界向けの主要機能
- オペレーター自動振分
- 顧客対応の支援AI
- 顧客記録の自動レポート
生活インフラ業界
Bright Pattern

引用元:Bright Pattern公式HP
(https://brightpattern.cba-japan.com/)
(https://brightpattern.cba-japan.com/)
- クレームが激増する
障害発生時の対応をカバー - 東京と大阪の2つのエリアでデータ同期しながら運用可能。特定エリアでの障害・災害発生時にも利用者を待たせることなく対応できます。
- チャットボットや自動音声で
24時間365日問い合わせに対応 - 24時間365日、チャットボットや自動音声が回答をしてくれます。問い合わせ対応を止めずに済み、クレーム阻止につながります。
生活インフラ業界向けの主要機能
- 通話待ち整理券
- AIチャットボット
- IVR(自動音声応答)
EC・小売業界
Re:lation

引用元:Re:lation公式HP
(https://ingage.jp/relation/)
(https://ingage.jp/relation/)
- 多様化した問い合わせ手段を
まとめて一元管理 - メール・LINE・電話・SNSなど10種にも及ぶ窓口を統合・管理。それぞれのツールへの行き来がなくなり、対応が一画面で完結します。
- 低コストで使える
EC向けチャットを搭載 - 使うほどコスト減になるEC向けチャットで簡単な対応を高速化。(3万通を超える場合は2円/通)セール時などの一時的なアクセス増も安心です。
EC・小売業界向けの主要機能
- 通話の自動文字起こし
- 単純作業のルール自動化
- 顧客情報・アドレス帳呼出