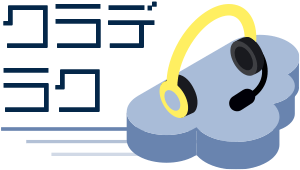WFMツールとは
「適切な人数のオペレーターを、適切なスキルセットで、適切な時間帯に配置する」—これは、コールセンター運営における永遠の課題です。この複雑な最適化問題を解決し、コストと顧客満足度の最適なバランスを実現する経営手法が「WFM(ワークフォース・マネジメント)」であり、それを実現するテクノロジーが「WFMツール」です。本記事では、部長クラス以上の責任者の方が知るべきWFMの戦略的重要性と、ツール導入の勘所を解説します。
WFM(ワークフォース・マネジメント)の基礎理解
WFMの定義と役割
WFM(ワークフォース・マネジメント)とは、日本語では「人員計画・要員管理」と訳され、企業の目標達成のために、人的リソースを科学的アプローチで最適に配置・管理する経営手法を指します。その役割は、コスト効率とサービス品質という二律背反の要素を両立させ、企業の生産性を最大化することにあります。
コールセンターで特にWFMが重視される理由
コールセンターは、時間帯や曜日、季節要因によって入電数が大きく変動する「需要変動が激しい」業務です。人員が不足すれば、顧客を待たせる「あふれ呼」が発生し機会損失や顧客満足度低下に直結します。逆に人員が過剰であれば、無駄な人件費が発生します。この需要と供給のギャップを最小化し、経営効率を最大化するために、コールセンターにおいてWFMは特に重要な経営管理手法とされています。
WFMツールとは?
WFMツールの概要
WFMツールとは、これまで担当者の経験と勘、そして膨大なExcel作業に頼っていたWFMのプロセスを、システムによって自動化・最適化するための専門的なソフトウェアです。過去の膨大なデータを基にした需要予測から、最適なシフト作成、リアルタイムの状況監視までを一気通貫で支援します。
Excelや従来手法との違い
Excelでの管理は、静的でリアルタイム性に欠け、複雑な条件(オペレーターのスキル、希望休など)を考慮したシフト作成には限界があります。一方、WFMツールは、AIなどを活用して高精度な予測を行い、多様な条件を瞬時に反映した最適なシフトを自動生成します。急な欠員や呼量の変動にも動的に対応できる点が、従来手法との決定的な違いです。
コールセンターにおけるWFMツール導入のメリット
運営工数の削減と効率化
WFMツールは、これまでスーパーバイザー(SV)が数日かけて行っていた呼量予測やシフト作成といった煩雑な作業を、数時間、あるいは数分にまで短縮します。これにより、管理者はより付加価値の高い業務(品質管理やオペレーター教育など)に時間を割けるようになり、センター全体の生産性が向上します。
応対品質とCX(顧客体験)の向上
高精度な需要予測に基づき、常に適正な数のオペレーターを配置できるため、顧客の待ち時間が大幅に短縮され、応答率が向上します。これにより、顧客がストレスなくサポートを受けられるようになり、CX(顧客体験)の向上に直接的に貢献します。
人件費の最適化とコスト削減
WFMツールによる人員配置の最適化は、過剰人員による無駄なコストや、人員不足による残業代の発生を防ぎます。人件費というコールセンター最大のコスト要素を、データに基づいて最適化できるため、経営に対するインパクトは非常に大きいと言えます。
オペレーター満足度・離職率低下への効果
オペレーターの希望休や勤務条件、スキルレベルを考慮した公平で透明性の高いシフトを自動で作成できます。これにより、オペレーターは自身の働き方に納得感を持ちやすくなり、エンゲージメントが向上。結果として、コールセンター業界の長年の課題である高い離職率の改善にも繋がります。
WFMツールの主な機能
呼量予測と必要人員の算出
過去のコンタクト履歴(入電数、メール数など)や季節性、キャンペーン情報などを基に、将来の業務量をAIが予測。その予測に基づき、設定したサービスレベル(例:応答率80%)を達成するために必要な人員数を時間帯別に算出します。
シフト作成とリアルタイム修正
算出された必要人員数と、オペレーターのスキル、契約条件、希望休などをパズルのように組み合わせ、最適なシフトを自動で作成します。また、当日の急な欠勤や想定外の呼量増減に対し、リアルタイムで人員の過不足を警告し、休憩時間の調整などを支援します。
オペレーターのスキル・属性管理
オペレーター一人ひとりが持つスキル(例:英語対応可能、特定商品の専門知識)や習熟度を管理し、シフト作成時に考慮します。これにより、「特定のスキルを持つ人がいない」といった事態を防ぎ、常に対応品質を維持できます。
業務進行のリアルタイム可視化
現在の応答率、待ち時間、オペレーターの稼働状況などをダッシュボードでリアルタイムに可視化します。センターの状況を即座に把握し、問題が発生した際に迅速な意思決定を下すことが可能になります。
データ分析とレポーティング機能
予測と実績の乖離、オペレーターの生産性、人件費の推移など、様々なデータを分析・レポート化します。これらのデータを基に、予測精度の改善や、より効率的なセンター運営に向けたPDCAサイクルを回すことができます。
コールセンター業務最適化におけるWFM戦略
予測精度の向上による顧客満足度改善
WFM戦略の根幹は予測精度にあります。予測精度が高まれば、常にジャストインタイムの人員配置が可能となり、顧客を待たせない体制が実現します。これは、顧客満足度という重要な経営指標を改善するための、データに基づいたアプローチです。
業務効率化とコスト構造の改革
WFMは単なる効率化ツールではなく、コスト構造を根本から改革する経営戦略です。勘や経験に頼った場当たり的な人員配置から脱却し、データドリブンで人件費を最適化する文化を組織に根付かせることが、持続的な競争優位性に繋がります。
働き方改革・オペレーター支援との結びつき
WFMによる柔軟なシフト作成は、時短勤務や在宅勤務といった多様な働き方を支援し、「働き方改革」を推進します。オペレーターが働きやすい環境を整備することは、ES(従業員満足度)を高め、それが最終的にCX(顧客体験)の向上に繋がるという好循環を生み出します。
WFMツール選定時のポイント
自社の課題・ニーズ整理
まず、「なぜWFMツールが必要なのか」を明確にします。「予測精度が低い」「シフト作成に時間がかかりすぎている」「残業代が多い」など、自社が抱える最も大きな課題を定義することが、ツール選定の出発点です。
ツール比較(機能・サポート・連携性)
各ツールが提供する機能を、自社の要件と照らし合わせて比較します。また、既存のコンタクトセンターシステム(PBX/ACD)との連携性や、導入後のベンダーによるサポート体制の手厚さも重要な評価項目です。
価格体系とROI(投資対効果)の確認
価格体系(ID課金、席数課金など)を理解し、自社の規模でどれくらいの費用がかかるかを試算します。その上で、導入によって見込まれるコスト削減効果(人件費、残業代など)を算出し、投資対効果(ROI)を経営層に提示できる準備が必要です。
トライアルやPoCでのテスト導入
本格導入の前に、小規模なチームでのトライアルやPoC(概念実証)を実施し、実際の操作性や予測精度、費用対効果を検証することが、導入失敗のリスクを避ける上で極めて有効です。
WFMツール × コンタクトセンターシステムの統合活用
既存コンタクトセンターシステムとの連携事例
多くのWFMツールは、既存のコンタクトセンターシステムからリアルタイムの稼働データを取得し、それを基に予測や人員配置の最適化を行います。このように、WFMツールは単体で機能するよりも、コールセンターシステムと連携することでその真価を発揮します。
WFM+CRM連動による顧客満足度向上
さらにCRMと連携させることで、例えば「大規模なマーケティングキャンペーンの開始日」といった情報をWFMツールが取り込み、問い合わせの急増を事前に予測してシフトを厚くするといった、より戦略的でプロアクティブな人員配置が可能になります。
マルチチャネル対応におけるWFMの必要性
現代のコンタクトセンターでは、電話だけでなくメールやチャットなど、複数のチャネルを一人のオペレーターが担当することも珍しくありません。WFMツールは、これら応答時間が異なる複数チャネルの業務量を統合的に予測・管理し、最適な人員配置を実現するために不可欠な存在です。
WFMツールの導入ステップ
現状分析と要件定義
現在のシフト作成プロセス、予測方法、管理工数などを可視化し、課題を洗い出します。その上で、新ツールで何を実現したいのか、具体的な要件を定義します。
ベンダー選定と比較
要件定義に基づき、複数のベンダーから提案と見積もりを取得します。機能、価格、サポート体制、実績などを多角的に比較し、2〜3社に絞り込みます。
トライアル導入・検証
選定したベンダーのツールを実際に利用し、操作性や効果を検証します。現場の管理者やオペレーターを巻き込み、フィードバックを収集することが重要です。
本格稼働と継続改善
導入効果を最大化するため、運用ルールを策定し、全社的なトレーニングを実施します。導入後も定期的にレポートを分析し、予測モデルのチューニングなど、継続的な改善活動を行います。
主なWFMツールと市場の動向
海外系ツール(Zendesk WFMなど)
Zendesk、NICE、Verintといった海外製ツールは、グローバルでの豊富な導入実績と、AIなどを活用した高度な機能を特徴とします。大規模センターや、最新技術を積極的に活用したい企業に向いています。
国内系ツール(国産ベンダーの特徴)
国産ベンダーのツールは、日本の商習慣や働き方に合わせたきめ細やかな機能や、手厚い日本語サポートを強みとしています。特に、導入後の伴走支援を重視する企業に適しています。
クラウド型 vs オンプレミス型の比較
現在の市場では、初期投資が不要で、常に最新機能を利用できるクラウド型が圧倒的な主流です。特別なセキュリティ要件がない限り、多くの企業にとってクラウド型が合理的な選択肢となります。
WFMツールで未来のコンタクトセンターをどう変えるか
AI活用による高度予測と自動化
今後、AI技術の進化により、WFMツールの予測精度はさらに向上し、シフト作成や勤怠管理は完全に自動化されていくでしょう。管理者はより創造的で戦略的な業務に集中できるようになります。
働き方の多様化とWFMの役割
在宅勤務やギグワークなど、働き方が多様化する中で、個々の事情に合わせた最適なシフトを組むWFMの役割はますます重要になります。多様な人材が活躍できる基盤を支える技術となります。
コンタクトセンターからCX経営への貢献
WFMツールが提供するデータは、単なる人員配置に留まらず、「どの程度のコストをかければ、顧客満足度が何%向上するのか」といった経営判断の材料となります。これにより、コンタクトセンターはコストセンターから、CX(顧客体験)経営をデータで支える戦略拠点へと進化します。
WFMツールはコールセンター経営の必須投資
WFMツールは、もはや一部の大規模センターだけのものではありません。人材不足と顧客期待の高度化が進む現代において、あらゆる規模のコールセンターにとって、その生産性と品質を左右する必須の経営投資です。そして、多くの高機能なコンタैक्टセンターシステムは、WFM機能を標準搭載、あるいはシームレスに連携可能です。個別のツール導入だけでなく、センター全体の最適化という視点から、ぜひ導入をご検討ください。
業界特有の課題を
解決できる製品を選ぼう
解決できる製品を選ぼう
コールセンタークラウドシステムが活用されている業界は幅広いため、製品選びを成功させるには、自社の業界に合った機能を備えている製品を見つけることが大切です。
当サイトでは、導入する業界別におすすめのコールセンタークラウドシステムをピックアップ。業界特有の課題をどのように解決できるのか、理由と併せて紹介しています。自社の業界にマッチする製品を見つけたい方は、ぜひチェックしてみてください。
業種別
クラウド型コールセンターシステム3選
クラウド型コールセンターシステム3選
コールセンターの運用を適正化し、事業成長を加速させられるクラウド型システム。業種・業界ごとの課題に応じて導入し、変化に強いコールセンターを構築しましょう。
金融・保険業界
Genesys Cloud CX

引用元:Genesys Cloud CX公式HP
(https://www.genesys.com/ja-jp)
(https://www.genesys.com/ja-jp)
- 強固なセキュリティ対策で
重要な顧客情報を守る - 複数の防御対策を掛け合わせ、企業ごとに固有の暗号化キーも採用。PCI DSS、GDPR、ISO 27001等、国際的な金融セキュリティ基準に準拠しています。
- セキュリティとAI活用で
顧客対応・監査の負担を削減 - AIが顧客情報を分析して適切なオペレーターをアサインし、初回解決率を向上。個別対応が重要なローン・信託相談の効率化に寄与します。
金融・保険業界向けの主要機能
- オペレーター自動振分
- 顧客対応の支援AI
- 顧客記録の自動レポート
生活インフラ業界
Bright Pattern

引用元:Bright Pattern公式HP
(https://brightpattern.cba-japan.com/)
(https://brightpattern.cba-japan.com/)
- クレームが激増する
障害発生時の対応をカバー - 東京と大阪の2つのエリアでデータ同期しながら運用可能。特定エリアでの障害・災害発生時にも利用者を待たせることなく対応できます。
- チャットボットや自動音声で
24時間365日問い合わせに対応 - 24時間365日、チャットボットや自動音声が回答をしてくれます。問い合わせ対応を止めずに済み、クレーム阻止につながります。
生活インフラ業界向けの主要機能
- 通話待ち整理券
- AIチャットボット
- IVR(自動音声応答)
EC・小売業界
Re:lation

引用元:Re:lation公式HP
(https://ingage.jp/relation/)
(https://ingage.jp/relation/)
- 多様化した問い合わせ手段を
まとめて一元管理 - メール・LINE・電話・SNSなど10種にも及ぶ窓口を統合・管理。それぞれのツールへの行き来がなくなり、対応が一画面で完結します。
- 低コストで使える
EC向けチャットを搭載 - 使うほどコスト減になるEC向けチャットで簡単な対応を高速化。(3万通を超える場合は2円/通)セール時などの一時的なアクセス増も安心です。
EC・小売業界向けの主要機能
- 通話の自動文字起こし
- 単純作業のルール自動化
- 顧客情報・アドレス帳呼出