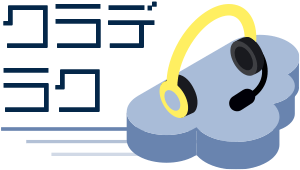コールセンターシステムの構成とは
コールセンターシステムの導入を成功させるには、機能の一つひとつを理解するだけでなく、それらがどのように連携し、全体としてどう機能するのかという「構成」を理解することが不可欠です。適切なシステム構成は、業務効率、顧客満足度、そして投資対効果(ROI)を大きく左右します。本記事では、コールセンターシステムの全体像を構成要素ごとに分解し、成果を出すための設計ポイントを経営層の視点から解説します。
コールセンターの基本システム構成
現代のコールセンターは、様々な専門システムが連携することで成り立っています。ここでは、その中核を担う構成要素とそれぞれの役割を解説します。
| PBX/ACD | 電話回線の接続・制御を担う交換機です。着信をスキルや稼働状況に応じて最適なオペレーターに自動で振り分ける(ルーティングする)役割を持ち、つながりやすさを左右する中核部分です。 |
|---|---|
| IVR | 自動音声応答システムです。用件に応じて番号入力で振り分けたり、音声認識で簡単な質問に自動で回答したりすることで、自己解決率の向上とオペレーターの負担軽減を実現します。 |
| CTI | 電話とコンピューターを連携させるシステムです。着信時に顧客情報をPC画面にポップアップ表示させ、オペレーターがスムーズに応対を開始できるよう支援します。 |
| CRM | 顧客情報や過去の応対履歴を一元管理するデータベースです。どのオペレーターが対応しても、一貫性のあるパーソナライズされた応対を可能にする、顧客接点の心臓部です。 |
| FAQ/ナレッジ | オペレーターが参照する「よくある質問と回答集」のシステムです。回答の標準化と迅速化を促し、応対品質の均一化と新人教育の効率化に貢献します。 |
| 録音・品質管理/QA | 全ての通話を録音し、管理者が聞き返したり、応対内容を評価したりするためのシステムです。コンプライアンス遵守と、オペレーターへの具体的な指導・育成に不可欠です。 |
| WFM | 過去のデータから将来の入電数を予測し、必要な人員数を算出して、最適なシフトを自動作成する人員最適化システムです。コストとサービスレベルのバランスを最適化します。 |
| 分析/BI | 応答率、平均処理時間、解決率といった様々なKPIデータを集計・可視化するツールです。センターの課題を発見し、データに基づいた改善活動を行うための意思決定を支援します。 |
| ダイヤラー | アウトバウンド業務で利用され、リストに基づき自動で発信するシステムです。オペレーターが繋がったコールにのみ集中できるため、架電効率を飛躍的に向上させます。 |
アーキテクチャの種類:オンプレミス vs クラウド
これらのシステム群をどのように構築・導入するかには、大きく分けてオンプレミス、クラウド、そして両者を組み合わせたハイブリッドの3つのアーキテクチャ(設計思想)があります。
クラウド(CCaaS)
ベンダーが提供するサービスをインターネット経由で利用する形態です。初期投資を抑え、短期間で導入できる手軽さと、事業規模に合わせて柔軟に拡張できる点が大きなメリット。常に最新機能を利用できる一方、カスタマイズの自由度やセキュリティ要件については、ベンダーの提供範囲内で検討する必要があります。
オンプレミス
自社内にサーバーなどのハードウェアを設置し、システムを構築する形態です。自社のセキュリティポリシーに準拠した強固な環境を構築でき、既存システムとの連携など、独自のカスタマイズを自由に行える点がメリット。ただし、高額な初期投資と、専門知識を持つ運用人材が必要です。
ハイブリッド/段階移行
既存のオンプレミス資産を活かしつつ、在宅勤務や新チャネル対応など、必要な機能のみをクラウドで補う形態です。リスクを抑えながら、段階的にクラウドへ移行していく現実的な選択肢として注目されています。
システム構成における重要設計ポイント
ネットワーク・音声品質の設計
コールセンターシステムの品質は、通話音声の品質に大きく左右されます。特に在宅勤務を導入する場合、従業員宅のインターネット回線の帯域や、安全な接続を担保する仕組み(SBCなど)の設計が、安定したサービス提供の生命線となります。
データ分析とKPIの設計
どのようなデータを収集し、何をKPIとして追うかを事前に設計することが重要です。応答率、平均処理時間(AHT)、一次解決率(FCR)、顧客満足度(NPS)といったKPI同士の相関関係を理解し、経営目標に直結する指標をダッシュボードで可視化する仕組みを構築します。
セキュリティとBCPの設計
顧客の個人情報を守るため、通信の暗号化や厳格なアクセス権限管理は必須です。また、自然災害やシステム障害に備え、拠点を冗長化したり、在宅勤務へスムーズに移行したりできるBCP(事業継続計画)を、システム構成の段階から組み込んでおく必要があります。
システムを支える「組織構成」の重要性
高度なシステムも、それを使いこなす組織がなければ価値を生みません。明確な指揮命令系統と、役割に応じた権限設計が、システム構成の効果を最大化します。
一般的な組織体制と役割
センター長が全体の戦略と予算を管理し、スーパーバイザー(SV)が日々のオペレーターの管理と育成を担う、といった役割分担を明確にします。システムの各機能(レポート閲覧、設定変更など)を、どの役職が担うのかも定義します。
権限設計とスキルマップ
「誰が、どのデータに、どこまでアクセスできるのか」という権限を厳格に設計することは、セキュリティの基本です。また、オペレーターのスキル(対応可能な製品、言語など)を可視化(スキルマップ化)し、それに基づいて着信を振り分けることで、応対品質を向上させます。
コールセンターの設計・構築 5つのステップ
1. 目標の設定
まず、コールセンターに求める役割(コスト削減か、売上貢献か、顧客満足度向上か)を定義し、応答率や解決率などの具体的な目標KPIを設定します。
2. 現状把握・課題の洗い出し
現在の業務フロー、人員体制、問い合わせ内容などをデータで分析し、「どこにボトルネックがあるのか」「何が課題なのか」を定量的に特定します。
3. 詳細な組織・体制の設計
目標達成に必要な席数やシフト、権限、教育体制、品質評価(QA)の基準などを具体的に設計します。
4. システムの構築・テスト
定義した要件に基づき、CTI、CRM、FAQなどの各システムを連携させ、構築します。一部のチームで試験運用(パイロットテスト)を行い、課題を洗い出します。
5. 運用体制の構築と改善
日々のKPIをモニタリングし、課題が見つかれば改善策を実行するPDCAサイクルを回す仕組みを構築します。定期的な改善会議体の設置などが有効です。
システム構成がもたらす経営メリット
オペレーター負担軽減と品質維持
FAQやCRMによる応対支援機能が、オペレーターの負担を軽減し、新人でも一定レベルの応対ができるよう支援します。これにより、応対品質の標準化と教育コストの削減を実現します。
顧客満足度の向上
IVRやACDが顧客を待たせることなく適切な担当者へ繋ぎ、CTIがスムーズな情報提供を支援することで、待ち時間の短縮と一次解決率(FCR)の向上を実現。これらは顧客満足度に直結します。
コスト最適化(TCO視点)
WFMによる人員配置の最適化や、FAQ・ボットによる自己解決率の向上が、センター最大のコストである人件費を削減。また、クラウド活用は設備投資や保守費用を抑制し、TCO(総保有コスト)を最適化します。
システム構成における注意点と失敗回避策
システム以外の必須設備・ツール
高品質なヘッドセット、十分なスペックのPC、安定したネットワーク回線など、システムを快適に利用するための物理的な設備も軽視できません。これらが不十分だと、システムの性能を最大限に引き出せません。
よくある失敗とその回避策
「使わない機能まで導入し、コストが高騰する」「現場が使いこなせず、Excel管理に戻ってしまう」「KPIが経営目標と連動していない」などが典型的な失敗例です。要件定義の段階で、必須機能とそうでない機能を見極め、現場を巻き込みながら導入を進めることが回避策となります。
目的・構成・組織の連携が成功の鍵
コールセンターシステムの構築は、単なるIT導入プロジェクトではありません。それは、「何を達成したいのか(目的)」「どのような道具立てで実現するのか(システム構成)」「誰がどのように使うのか(組織)」という三位一体の改革です。これらの整合性が取れて初めて、システムは真の価値を発揮し、企業の競争力を高める戦略的基盤となります。部分最適に陥らず、常に全体像を意識した設計を心がけましょう。
業界特有の課題を
解決できる製品を選ぼう
解決できる製品を選ぼう
コールセンタークラウドシステムが活用されている業界は幅広いため、製品選びを成功させるには、自社の業界に合った機能を備えている製品を見つけることが大切です。
当サイトでは、導入する業界別におすすめのコールセンタークラウドシステムをピックアップ。業界特有の課題をどのように解決できるのか、理由と併せて紹介しています。自社の業界にマッチする製品を見つけたい方は、ぜひチェックしてみてください。
業種別
クラウド型コールセンターシステム3選
クラウド型コールセンターシステム3選
コールセンターの運用を適正化し、事業成長を加速させられるクラウド型システム。業種・業界ごとの課題に応じて導入し、変化に強いコールセンターを構築しましょう。
金融・保険業界
Genesys Cloud CX

引用元:Genesys Cloud CX公式HP
(https://www.genesys.com/ja-jp)
(https://www.genesys.com/ja-jp)
- 強固なセキュリティ対策で
重要な顧客情報を守る - 複数の防御対策を掛け合わせ、企業ごとに固有の暗号化キーも採用。PCI DSS、GDPR、ISO 27001等、国際的な金融セキュリティ基準に準拠しています。
- セキュリティとAI活用で
顧客対応・監査の負担を削減 - AIが顧客情報を分析して適切なオペレーターをアサインし、初回解決率を向上。個別対応が重要なローン・信託相談の効率化に寄与します。
金融・保険業界向けの主要機能
- オペレーター自動振分
- 顧客対応の支援AI
- 顧客記録の自動レポート
生活インフラ業界
Bright Pattern

引用元:Bright Pattern公式HP
(https://brightpattern.cba-japan.com/)
(https://brightpattern.cba-japan.com/)
- クレームが激増する
障害発生時の対応をカバー - 東京と大阪の2つのエリアでデータ同期しながら運用可能。特定エリアでの障害・災害発生時にも利用者を待たせることなく対応できます。
- チャットボットや自動音声で
24時間365日問い合わせに対応 - 24時間365日、チャットボットや自動音声が回答をしてくれます。問い合わせ対応を止めずに済み、クレーム阻止につながります。
生活インフラ業界向けの主要機能
- 通話待ち整理券
- AIチャットボット
- IVR(自動音声応答)
EC・小売業界
Re:lation

引用元:Re:lation公式HP
(https://ingage.jp/relation/)
(https://ingage.jp/relation/)
- 多様化した問い合わせ手段を
まとめて一元管理 - メール・LINE・電話・SNSなど10種にも及ぶ窓口を統合・管理。それぞれのツールへの行き来がなくなり、対応が一画面で完結します。
- 低コストで使える
EC向けチャットを搭載 - 使うほどコスト減になるEC向けチャットで簡単な対応を高速化。(3万通を超える場合は2円/通)セール時などの一時的なアクセス増も安心です。
EC・小売業界向けの主要機能
- 通話の自動文字起こし
- 単純作業のルール自動化
- 顧客情報・アドレス帳呼出