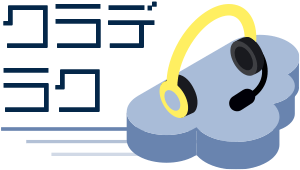コールセンターシステムの費用と料金相場
コールセンターシステムの導入を検討されている経営層・部長クラスの皆様。「導入したいが、費用がいくらかかるか分からない」「料金体系が複雑で、自社に最適なプランが選べない」といったお悩みをお持ちではないでしょうか。
本記事では、料金体系の全体像と相場、そして導入形態や機能ごとのコストインパクトを徹底解説します。
コールセンターシステムの料金体系と内訳
料金構成の全体像と内訳
コールセンターシステムの費用は、大きく分けて3つの要素で構成されています。1つ目はサーバー構築や設定にかかる「初期費用」、2つ目はシステムのライセンス料や保守料として毎月発生する「月額費用(ランニングコスト)」、そして3つ目が通話料や特定の機能を追加する際の「オプション費用」です。
近年では、高額なサーバー購入が不要で初期費用を大幅に抑えられるクラウド型が主流となっています。しかし、月額費用やオプション費用を含めたトータルコストで比較検討しなければ、長期的に見て割高になってしまうケースもあります。表面的な価格だけでなく、総額でどれだけのコストがかかるのかを把握することが重要です。
コストを決定づける2つの大きな要因
システムの総コストは、主に2つの要因によって大きく変動します。1つ目の要因は【導入形態】です。自社でサーバーを保有・管理する「オンプレミス型」は、初期費用が高額になる一方、セキュリティやカスタマイズの自由度が高いのが特徴です。対して「クラウド型」は、初期費用が安くスピーディに導入できる反面、月額費用が継続的に発生します。
2つ目の要因は【センターの規模と利用ユーザー数】です。当然ながら、オペレーターの席数やシステムを利用するユーザー数が多くなるほど費用は高くなります。例えば、5席程度の小規模センターであれば月額数万円から導入可能ですが、100席を超える大規模センターでは数百万円規模になることもあります。自社の事業規模や将来の拡張計画に合わせて、最適な形態と規模を見極める必要があります。
【導入形態別】コールセンターシステムの費用相場
クラウド型コールセンターシステム(CTI)の費用相場
クラウド型の費用相場は、初期費用が無料〜数十万円、月額費用が1ID(ユーザー)あたり数千円〜1.5万円程度(2025年10月時点・編集チーム調べ)が目安です。サーバー構築が不要なため初期投資を大幅に抑制でき、申し込みから数日〜数週間という短期間で導入できるのが最大のメリットです。また、事業の成長に合わせてID数を柔軟に増減できる拡張性の高さや、災害時にも事業を継続しやすいBCP対策の観点からも優れています。
クラウド型を選ぶ際の判断の視点として、月額料金の課金体系をしっかり確認しましょう。ユーザー数に応じた「ID課金」のほか、同時に通話できる数で決まる「チャネル課金」、席数で決まる「席課金」など、ベンダーによって様々です。自社の運用スタイルに最も合った課金体系を選ぶことが、コストの無駄をなくす鍵となります。
オンプレミス型コールセンターシステム(CTI)の費用相場
オンプレミス型の費用相場は、初期費用が数百万円〜数千万円規模(2025年10月時点・編集チーム調べ)となり、導入後もサーバーの維持管理やメンテナンスのための保守・運用費用が別途発生します。初期投資は高額ですが、自社の基幹システムとの高度な連携や、業務に合わせた独自のカスタマイズを自由に行える点が大きなメリットです。また、閉域網でシステムを構築するため、非常に強固なセキュリティ環境を実現できます。
オンプレミス型を検討する際は、TCO(総保有コスト)の視点が不可欠です。初期費用だけでなく、サーバーの更新費用、ソフトウェアのアップデート費用、管理を担当する社内人件費など、5年〜10年単位の長期的な視点で総コストを算出する必要があります。短期的な費用だけでなく、長期にわたる運用まで見据えた上で、クラウド型との費用対効果を比較判断することが求められます。
費用に直結する「機能別」の料金体系と選び方
基本機能と追加料金が発生しやすい機能
コールセンターシステムの料金は、利用できる機能によっても変動します。多くのシステムでは、着信を自動で振り分ける「ACD」や自動音声応答の「IVR」、全通話を記録する「通話録音」といった基本機能は、月額の基本料金内に含まれています。
一方、顧客管理システムと連携させる「CRM/SFA連携」や、オペレーターの配置を最適化する「WFM」、通話内容をテキスト化する「音声認識」、さらには「AIチャットボット」といった高度な機能は、追加オプションとして別途料金が発生するのが一般的です。これらのオプションは月額数万円から数十万円かかることもあり、総コストに大きく影響します。自社の課題解決に本当に必要な機能を見極め、費用対効果を慎重に判断することが大切です。
ツール別に見るコスト構造(CTI以外の主要システム)
コールセンターの運営には、CTI以外にも様々なシステムが連携して機能します。例えば「CRM/SFA」はユーザー数に応じたID課金が基本で、コールセンター連携には特定のライセンスプランが必要になる場合があります。また、「FAQシステム」や「チャットボット」は、作成するコンテンツ数や利用量(PV数、セッション数)など、ツールによって多様な課金形態が存在します。
これらのシステムを個別に導入し連携させる場合、それぞれの月額費用を合算してトータルコストを試算する必要があります。多機能なコールセンターシステムの中には、CRMやFAQの機能を標準搭載しているものもあります。自社の要件と照らし合わせ、個別に導入するか、オールインワンのシステムを選ぶか、総コストの観点から比較検討しましょう。
見落としがちな「通信費用」と「端末費用」の考慮
システムの利用料以外にも、見落としがちなコストが2つあります。1つは「通話料などの通信費用」です。固定電話への発信、携帯電話への発信、フリーダイヤルの着信など、回線の種類によって料金は異なります。ベンダーが提供する回線を利用する場合は、その料金体系(定額制か従量制か)もしっかり確認しましょう。
もう1つは「端末費用」です。オペレーターが業務で使用するPCやヘッドセット、安定したインターネット環境を整備するためのネットワーク機器なども、システム導入に伴って発生するコストです。特に在宅コールセンターを構築する場合は、これらの端末費用も予算に含めて計画する必要があります。
費用対効果を最大化するための導入・選定戦略
導入フェーズにおけるコスト削減のポイント
導入時のコストを最適化するためには、まず機能の要件定義が重要です。「絶対にないと業務が回らない必須機能」と、「あると便利だが、なくても何とかなるあれば良い機能」を明確に切り分けましょう。多機能なプランは魅力的ですが、使わない機能のために高い費用を払うのは避けるべきです。
特にクラウド型の場合、最初は最小限の機能で始める「スモールスタート」が有効です。運用しながら本当に必要な機能が見えてきた段階で、オプションを追加していくことで、無駄な投資リスクを抑制できます。また、ベンダーにRFP(提案依頼書)を提出する際は、必ず「費用の詳細な内訳」の提出を求めるようにしましょう。何にいくらかかっているのかを明確にすることで、価格の妥当性を判断しやすくなります。
中長期的な視点で判断すべきコスト要素
費用対効果は、導入時の直接的なコストだけで測れるものではありません。例えば、システム導入によってオペレーターの業務が効率化されれば、採用コストや研修にかかる教育コストを削減できます。また、電話のつながりやすさ(応答率)が改善されれば、顧客を待たせることによる「機会損失コスト」の低減にも繋がり、売上向上に貢献します。
さらに、ベンダーが提供するサポート体制の価値も費用に含めて評価すべきです。トラブル発生時に迅速に対応してくれる手厚いサポート(たとえ有償であっても)は、業務停止リスクを回避し、結果的にコスト削減に繋がります。目先の価格だけでなく、こうした間接的なコスト削減効果や事業貢献まで含めた、中長期的な視点で投資価値を判断することが成功の鍵です。
導入フェーズにおけるコスト削減のポイント
費用対効果は、導入時の直接的なコストだけで測れるものではありません。例えば、システム導入によってオペレーターの業務が効率化されれば、採用コストや研修にかかる教育コストを削減できます。また、電話のつながりやすさ(応答率)が改善されれば、顧客を待たせることによる「機会損失コスト」の低減にも繋がり、売上向上に貢献します。
さらに、ベンダーが提供するサポート体制の価値も費用に含めて評価すべきです。トラブル発生時に迅速に対応してくれる手厚いサポート(たとえ有償であっても)は、業務停止リスクを回避し、結果的にコスト削減に繋がります。目先の価格だけでなく、こうした間接的なコスト削減効果や事業貢献まで含めた、中長期的な視点で投資価値を判断することが成功の鍵です。
失敗しないためのベンダー選定プロセスと注意点
最適なベンダーを選定するためには、必ず複数社から相見積もりを取り、サービス内容と費用を比較検討しましょう。その際、ただ金額を比較するだけでなく、提示された費用の「根拠」を各社に詳しくヒアリングすることが重要です。同じ機能名でも、ベンダーによって性能やカバー範囲が異なる場合があります。
そして最も大切なのは、費用だけで判断しないことです。安価なシステムは魅力的ですが、機能の拡張性や将来的なビジネスの成長に対応できる柔軟性に欠ける場合があります。自社の5年後、10年後を見据え、事業戦略のパートナーとして共に成長していける拡張性やサポート体制を持っているか、という視点でベンダーを総合的に評価しましょう。
導入形態と機能のバランスが「適正価格」を生む
コールセンターシステムの費用は、導入形態、センター規模、そして搭載する機能の組み合わせによって大きく変動します。高機能で高価なシステムが、必ずしも自社にとって最適とは限りません。「適正価格」とは、自社の事業フェーズとコールセンターに求める役割、そして解決したい課題に対して、過不足のない機能とサポートを備えたシステムの価格です。本記事で解説したポイントを参考に、ぜひ貴社にとって最も費用対効果の高いシステムを見つけてください。
具体的なシステムの比較検討を進めたい方は、当サイトの「クラウド型コールセンターシステム徹底比較」の記事も合わせてご覧ください。また、多くのベンダーが提供している「無料トライアル」を活用して、実際の操作性を試してみるのもおすすめです。
業界特有の課題を
解決できる製品を選ぼう
解決できる製品を選ぼう
コールセンタークラウドシステムが活用されている業界は幅広いため、製品選びを成功させるには、自社の業界に合った機能を備えている製品を見つけることが大切です。
当サイトでは、導入する業界別におすすめのコールセンタークラウドシステムをピックアップ。業界特有の課題をどのように解決できるのか、理由と併せて紹介しています。自社の業界にマッチする製品を見つけたい方は、ぜひチェックしてみてください。
業種別
クラウド型コールセンターシステム3選
クラウド型コールセンターシステム3選
コールセンターの運用を適正化し、事業成長を加速させられるクラウド型システム。業種・業界ごとの課題に応じて導入し、変化に強いコールセンターを構築しましょう。
金融・保険業界
Genesys Cloud CX

引用元:Genesys Cloud CX公式HP
(https://www.genesys.com/ja-jp)
(https://www.genesys.com/ja-jp)
- 強固なセキュリティ対策で
重要な顧客情報を守る - 複数の防御対策を掛け合わせ、企業ごとに固有の暗号化キーも採用。PCI DSS、GDPR、ISO 27001等、国際的な金融セキュリティ基準に準拠しています。
- セキュリティとAI活用で
顧客対応・監査の負担を削減 - AIが顧客情報を分析して適切なオペレーターをアサインし、初回解決率を向上。個別対応が重要なローン・信託相談の効率化に寄与します。
金融・保険業界向けの主要機能
- オペレーター自動振分
- 顧客対応の支援AI
- 顧客記録の自動レポート
生活インフラ業界
Bright Pattern

引用元:Bright Pattern公式HP
(https://brightpattern.cba-japan.com/)
(https://brightpattern.cba-japan.com/)
- クレームが激増する
障害発生時の対応をカバー - 東京と大阪の2つのエリアでデータ同期しながら運用可能。特定エリアでの障害・災害発生時にも利用者を待たせることなく対応できます。
- チャットボットや自動音声で
24時間365日問い合わせに対応 - 24時間365日、チャットボットや自動音声が回答をしてくれます。問い合わせ対応を止めずに済み、クレーム阻止につながります。
生活インフラ業界向けの主要機能
- 通話待ち整理券
- AIチャットボット
- IVR(自動音声応答)
EC・小売業界
Re:lation

引用元:Re:lation公式HP
(https://ingage.jp/relation/)
(https://ingage.jp/relation/)
- 多様化した問い合わせ手段を
まとめて一元管理 - メール・LINE・電話・SNSなど10種にも及ぶ窓口を統合・管理。それぞれのツールへの行き来がなくなり、対応が一画面で完結します。
- 低コストで使える
EC向けチャットを搭載 - 使うほどコスト減になるEC向けチャットで簡単な対応を高速化。(3万通を超える場合は2円/通)セール時などの一時的なアクセス増も安心です。
EC・小売業界向けの主要機能
- 通話の自動文字起こし
- 単純作業のルール自動化
- 顧客情報・アドレス帳呼出