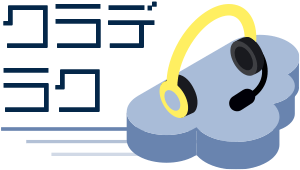コールセンターシステムのセキュリティ対策
個人情報漏洩のニュースが後を絶たない現代、顧客データを大量に取り扱うコールセンターのセキュリティ対策は、もはや単なるIT部門の課題ではありません。それは、企業のブランド価値と社会的信頼を左右する、極めて重要な経営リスクです。本記事では、部長クラス以上の責任者の方が知るべき、コールセンターにおけるセキュリティの全体像と、未来の脅威から事業を守るための戦略的アプローチを解説します。
なぜ今、コールセンターのセキュリティ再構築が必要なのか
従来型セキュリティの限界(境界防御モデルの崩壊)
従来、企業のセキュリティは「境界防御」という考え方が主流でした。これは、オフィスのネットワークを城壁で囲み、外部からの侵入を防ぐというものです。しかし、クラウドサービスの利用や在宅勤務が当たり前になった今、守るべきデータの場所やアクセスする従業員の場所が社内外に分散し、この「城壁」は意味をなさなくなっています。
攻撃手法の高度化と人的ミスリスクの増大
サイバー攻撃の手法は年々高度化・巧妙化しており、フィッシング詐欺や標的型攻撃など、従業員を狙った攻撃が増加しています。また、悪意のないオペレーターによるメールの誤送信やUSBメモリの紛失といった、ヒューマンエラーに起因する情報漏洩リスクも依然として大きな課題です。
環境変化(在宅・BPO・SaaS連携)がもたらす新リスク
在宅勤務、外部委託(BPO)、そしてCRMなど複数のSaaSを連携させる業務環境は、利便性を向上させる一方で、新たなセキュリティリスクを生み出します。管理外のネットワークからのアクセスや、保護されていない個人PCの利用、連携するSaaSの脆弱性など、攻撃者にとっての侵入口(アタックサーフェス)が爆発的に増加しているのが現状です。
コールセンター特有のセキュリティリスクとは
コールセンターは、顧客の氏名、住所、電話番号、さらにはクレジットカード情報といった機密情報が集中する場所です。この「情報の集中」と「人の多さ」という構造が、特有のリスクを生み出します。
オペレーターによる個人情報の誤送信・持ち出し
悪意の有無にかかわらず、オペレーターが顧客情報を誤った宛先に送信してしまったり、不正にデータを持ち出したりする内部不正のリスクです。組織の目が届きにくい環境では、このリスクはさらに高まります。
在宅勤務環境における盗聴・覗き見リスク
セキュリティ対策が不十分な家庭のWi-Fiネットワークを介した通信の盗聴や、公共の場での作業中の画面の覗き見(ショルダーハッキング)、家族や同居人による情報の聞き取りなど、オフィスでは想定しなかった物理的なリスクが発生します。
システム間連携によるデータ流出リスク
コールセンターシステムとCRM、あるいはその他の業務システムを連携させる際、APIの認証設定の不備や、連携先のシステムの脆弱性を突かれて、データが外部に流出するリスクです。
セキュリティ対策の3本柱「ルール・人・技術」
堅牢なセキュリティ体制は、特定の技術だけで実現できるものではありません。「ルール」「人」「技術」の3つの要素が一体となって機能することが不可欠です。
ルール(ガバナンスと運用設計)
情報セキュリティポリシーの策定、アクセス権限のルール化、インシデント発生時の報告・対応プロセスの標準化など、組織としての意思決定と行動の指針を定めます。
人(教育・権限・モラル)
全従業員に対する継続的なセキュリティ教育の実施、必要最小限の権限付与(ミニマム・パーミッション)の徹底、そして高い倫理観を醸成する組織文化の構築が求められます。
技術(ゼロトラスト・多要素認証・暗号化)
ルールを強制し、人をミスから守るための技術的な仕組みです。後述するゼロトラストの考え方に基づき、多要素認証(MFA)やデータの暗号化、アクセスログの監視などを実装します。
コールセンターシステムに求められる13のセキュリティ要件
堅牢なコールセンターを構築するためには、以下のような多岐にわたるセキュリティ要件を考慮する必要があります。
- ガバナンス・リスク管理
- 資産・構成管理
- 脆弱性管理
- 特権管理
- データ保護
- マルウェア対策
- 通信の暗号化・ゼロトラスト通信
- アカウント・認証管理
- アクセス制御・監査ログ
- インシデント対応・フォレンジック
- 物理的セキュリティ(在宅対応含む)
- 脅威インテリジェンス・脆弱性情報活用
- セキュリティ教育・啓発活動
ゼロトラストの思想とSASEの台頭
ゼロトラストとは何か
ゼロトラストとは、「何も信用しない(Never Trust, Always Verify)」を前提とするセキュリティの考え方です。社内ネットワークからのアクセスであっても、すべてを信頼できないものとみなし、データやアプリケーションにアクセスするたびに、ユーザーの本人確認とデバイスの安全性を厳格に検証します。
SASE(サッシー)とは?クラウド時代の新防御モデル
SASE(Secure Access Service Edge)とは、ゼロトラストの思想を実現するための一つのソリューション形態です。従来は個別の機器で提供されていたネットワーク機能とセキュリティ機能を、単一のクラウドサービスとして提供します。これにより、従業員がどこにいても、同じセキュリティポリシーの下で安全に社内リソースやクラウドサービスにアクセスできるようになります。
SASEのメリット・デメリット
メリットは、場所を問わない一貫したセキュリティの実現と、運用管理の簡素化です。一方、デメリットとしては、導入には専門的な知見が必要であることや、特定のベンダーに依存するリスクが挙げられます。
導入時に確認すべき3つのポイント
SASEを導入する際は、既存のネットワークインフラとの互換性、自社のセキュリティポリシーとの整合性、そして導入後の運用監視体制を誰が担うのか、という3点を確認することが重要です。
実例で見るセキュリティ対策強化の成功事例
動画配信プラットフォーム企業の在宅コールセンター化事例
ある動画配信プラットフォーム企業は、事業の急拡大に伴い、在宅コールセンターへの移行を決定。ゼロトラストの考え方に基づいたクラウド型コールセンターシステムを導入し、多要素認証とデバイス制御を徹底。これにより、オペレーターは自宅からでも、顧客の決済情報などを安全に取り扱うことができる体制を構築しました。
BPO事業者によるゼロトラスト導入事例
複数のクライアント企業の業務を請け負うあるBPO事業者は、SASEを導入。クライアントごとにアクセスできる情報やアプリケーションを厳格に分離し、オペレーターがどの場所からどのクライアントの業務を行っても、統一された高いセキュリティを担保できる仕組みを実現。これが新たな信頼となり、新規顧客獲得にも繋がりました。
クラウドPBXとCRM連携環境でのデータ保護体制
ある金融サービス企業では、クラウドPBXとCRMを連携させるにあたり、個人情報をマスキング(匿名化)する機能を導入。オペレーターは顧客の応対履歴を参照できますが、クレジットカード番号などの機密情報は表示されない仕組みを構築し、内部不正や情報漏洩のリスクを大幅に低減しました。
セキュリティ対策を実践する際の3つのポイント
トラブル発生時の初動対応を標準化しておく
セキュリティインシデントは「いつか必ず起きる」という前提で、発生時の報告ルート、責任者、顧客への告知手順などを具体的に定めたインシデントレスポンス計画を策定し、定期的に訓練しておくことが、被害を最小限に抑える鍵です。
セキュリティ設計を“業務プロセス”と一体化する
セキュリティを後付けの機能と捉えるのではなく、オペレーターの採用から退職までの人の流れや、情報のライフサイクルといった業務プロセスそのものに、セキュリティの考え方を組み込むことが、形骸化しない対策に繋がります。
システム選定時に「セキュリティ要件」を明示的に評価する
ベンダー選定の際、「セキュリティは万全です」といった曖昧な回答で満足してはいけません。自社が求めるセキュリティ要件をRFP(提案依頼書)に明記し、第三者機関による認証の有無や、具体的な機能の実装方法まで踏み込んで評価する姿勢が不可欠です。
セキュリティ強化を支援する最新のコールセンターシステム機能
最新のコールセンターシステムには、セキュリティを強化するための機能が多数搭載されています。
クラウドPBXの通信暗号化・ログ監査機能
顧客とオペレーター間の通話内容や、オペレーターのPCとサーバー間の通信を暗号化(TLS/SRTP)する機能、そして「誰が・いつ・どの情報にアクセスしたか」を克明に記録する監査ログ機能は、今や必須の機能です。
CRM連携による個人情報管理の強化
CRMと連携することで、オペレーターの役職や担当業務に応じて、閲覧・編集できる顧客情報の範囲を厳格に制御できます。不要な情報へのアクセスを根本から断つことが、漏洩リスクを低減します。
音声認証・AI不正検知などの最新技術
顧客本人の声で認証を行う「音声認証(声紋認証)」や、オペレーターの不審なPC操作や会話内容をAIが検知して管理者にアラートを出す「不正検知」など、AIを活用した新しいセキュリティ技術も登場しています。
経営層が握るべき「セキュリティ=経営リスク」視点
コールセンターのセキュリティ対策は、もはやIT担当者だけの責任範囲ではありません。顧客からの信頼、社会的な信用、そしてブランド価値そのものを守るための、極めて重要な経営課題です。セキュリティへの投資を単なる「コスト」と捉えるか、事業継続と成長のための「戦略的投資」と捉えるか。その視点こそが、これからの時代を勝ち抜く企業の競争力を左右します。自社の事業を守るため、今こそセキュリティ体制の再構築に向けた一歩を踏み出しましょう。
業界特有の課題を
解決できる製品を選ぼう
解決できる製品を選ぼう
コールセンタークラウドシステムが活用されている業界は幅広いため、製品選びを成功させるには、自社の業界に合った機能を備えている製品を見つけることが大切です。
当サイトでは、導入する業界別におすすめのコールセンタークラウドシステムをピックアップ。業界特有の課題をどのように解決できるのか、理由と併せて紹介しています。自社の業界にマッチする製品を見つけたい方は、ぜひチェックしてみてください。
業種別
クラウド型コールセンターシステム3選
クラウド型コールセンターシステム3選
コールセンターの運用を適正化し、事業成長を加速させられるクラウド型システム。業種・業界ごとの課題に応じて導入し、変化に強いコールセンターを構築しましょう。
金融・保険業界
Genesys Cloud CX

引用元:Genesys Cloud CX公式HP
(https://www.genesys.com/ja-jp)
(https://www.genesys.com/ja-jp)
- 強固なセキュリティ対策で
重要な顧客情報を守る - 複数の防御対策を掛け合わせ、企業ごとに固有の暗号化キーも採用。PCI DSS、GDPR、ISO 27001等、国際的な金融セキュリティ基準に準拠しています。
- セキュリティとAI活用で
顧客対応・監査の負担を削減 - AIが顧客情報を分析して適切なオペレーターをアサインし、初回解決率を向上。個別対応が重要なローン・信託相談の効率化に寄与します。
金融・保険業界向けの主要機能
- オペレーター自動振分
- 顧客対応の支援AI
- 顧客記録の自動レポート
生活インフラ業界
Bright Pattern

引用元:Bright Pattern公式HP
(https://brightpattern.cba-japan.com/)
(https://brightpattern.cba-japan.com/)
- クレームが激増する
障害発生時の対応をカバー - 東京と大阪の2つのエリアでデータ同期しながら運用可能。特定エリアでの障害・災害発生時にも利用者を待たせることなく対応できます。
- チャットボットや自動音声で
24時間365日問い合わせに対応 - 24時間365日、チャットボットや自動音声が回答をしてくれます。問い合わせ対応を止めずに済み、クレーム阻止につながります。
生活インフラ業界向けの主要機能
- 通話待ち整理券
- AIチャットボット
- IVR(自動音声応答)
EC・小売業界
Re:lation

引用元:Re:lation公式HP
(https://ingage.jp/relation/)
(https://ingage.jp/relation/)
- 多様化した問い合わせ手段を
まとめて一元管理 - メール・LINE・電話・SNSなど10種にも及ぶ窓口を統合・管理。それぞれのツールへの行き来がなくなり、対応が一画面で完結します。
- 低コストで使える
EC向けチャットを搭載 - 使うほどコスト減になるEC向けチャットで簡単な対応を高速化。(3万通を超える場合は2円/通)セール時などの一時的なアクセス増も安心です。
EC・小売業界向けの主要機能
- 通話の自動文字起こし
- 単純作業のルール自動化
- 顧客情報・アドレス帳呼出