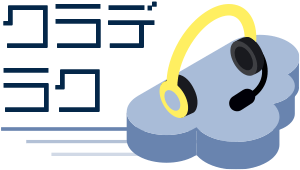コールセンターシステムのメリットとデメリット
コールセンターの運営において、コスト削減、生産性、顧客満足度、そしてオペレーターの離職率といった課題は、多くの経営層にとって重要な関心事ではないでしょうか。
これらの課題を解決する一手として注目されるのが「コールセンターシステム」です。この記事では、経営視点から見たコールセンターシステムのメリット・デメリットを徹底解説。導入の失敗を避け、費用対効果を最大化するための選定ポイントまで網羅的にご紹介します。
コールセンターシステムとは?今さら聞けない基本と必要性
コールセンターシステムとは、電話応対業務を効率化し、顧客情報を一元管理するための仕組みです。主な機能として、電話とコンピューターを連携させる「CTI」や、顧客情報を管理・活用する「CRM」などがあります。
従来のコールセンターでは、オペレーター個人の経験や記憶に頼ることが多く、担当者が変わると対応品質にばらつきが出る「属人化」が課題でした。また、どの顧客からいつ電話があったかといった情報が共有されず、ビジネスチャンスを逃す「機会損失」も少なくありませんでした。
現代のビジネスにおいて、顧客一人ひとりとの関係性を深めることは不可欠です。コールセンターシステムは、これらの課題を解決し、データを活用した戦略的な顧客対応を実現するための経営基盤として、その必要性が高まっています。
コールセンターシステムの戦略的メリット5選【経営層必見】
生産性の向上とコスト構造の最適化
コールセンターシステムは、業務の自動化を通じて生産性を飛躍的に向上させます。例えば「ACD(着信呼自動分配)」は、問い合わせ内容やオペレーターのスキルに応じて着信を自動で振り分ける機能です。また、「IVR(自動音声応答)」が初期対応を自動化することで、オペレーターはより複雑な問い合わせに集中できます。
さらに、CRMと連携した「ポップアップ機能」は、着信と同時に顧客情報をPC画面に表示させるため、本人確認や状況把握の時間を大幅に削減できます。これらの機能は、一人あたりの応対効率を高め、結果として人件費という最大のコスト構造を最適化することに直結します。
顧客満足度(CS)とLTVの最大化
顧客満足度の向上は、企業の持続的な成長に欠かせません。コールセンターシステムは、過去の応対履歴や購入履歴を一元管理し、どのオペレーターが対応してもスムーズで一貫性のあるサービス提供を可能にします。顧客は何度も同じ説明をする必要がなくなり、ストレスのない快適な顧客体験を得ることができます。
また、「通話録音・分析機能」を活用すれば、オペレーターの話し方や言葉遣いを客観的に評価し、応対品質の平準化と向上を図れます。質の高い対応は顧客の信頼を生み、リピート購入や長期的なファン化(LTV:顧客生涯価値の向上)へと繋がります。単なる問い合わせ窓口ではなく、顧客との関係を強化する戦略拠点として機能させることが可能です。
データドリブン経営の実現
経営判断の精度を高めるためには、客観的なデータに基づく意思決定が不可欠です。コールセンターシステムは、これまで把握しづらかった様々なデータを可視化します。例えば、電話のつながりやすさを示す「応答率」や、オペレーターが顧客対応にどれだけ時間を使っているかを示す「稼働率」といった重要業績評価指標(KPI)をリアルタイムで分析でき、人員配置の最適化や課題の早期発見が可能になります。
さらに、通話録音された「VOC(顧客の声)」をテキスト化・分析することで、商品開発やサービス改善に活かす貴重なインサイトを得られます。勘や経験に頼る経営から脱却し、データに基づいた戦略的な経営(データドリブン経営)を実現する上で、コールセンターシステムは強力な武器となります。
従業員満足度(ES)向上と離職率の改善
コールセンター業界の長年の課題である高い離職率は、採用・教育コストの増大を招きます。システム導入は、オペレーターの業務負荷を軽減し、働きやすい環境を構築することで、この問題にアプローチします。例えば、FAQシステムやマニュアルの共有機能は、新人オペレーターでも安心して業務に取り組める環境を提供します。
また、応対件数や時間といった客観的なデータに基づいて評価を行えるため、公平な評価制度の構築がしやすくなり、従業員のモチベーション向上に繋がります。近年では、クラウド型のシステムを選ぶことで在宅勤務(テレワーク)にも対応でき、多様な働き方を実現することも可能です。従業員満足度(ES)の向上は、定着率の改善だけでなく、応対品質の向上にも繋がり、結果的に顧客満足度の向上にも貢献します。
BCP対策とコンプライアンスの強化
自然災害やパンデミックなど、不測の事態が発生した際に事業を継続させるためのBCP(事業継続計画)対策は、現代企業にとって必須です。オンプレミス型(自社設置型)と異なり、クラウド型のコールセンターシステムはインターネット環境さえあれば場所を問わずに業務を継続できます。オフィスが機能しなくなった場合でも、オペレーターが自宅から対応できるため、事業停止のリスクを大幅に軽減します。
また、コンプライアンスの観点からもシステムは重要です。「通話録音機能」は、「言った・言わない」といったトラブルを未然に防ぐための重要な証跡となります。顧客との約束事を正確に記録し、万が一の際の事実確認や法的リスクへの備えとして、企業の信頼性を守る役割を果たします。
コールセンターシステムのデメリットと克服法
導入・運用コストが発生する
コールセンターシステムの導入には、当然ながらコストが発生します。特に自社でサーバーを構築するオンプレミス型は数百万円以上の初期費用がかかることもあり、クラウド型は初期費用を抑えられるものの、ライセンス数に応じた月額費用が継続的に発生します。
このコスト面の課題に対しては、まず導入によってどれだけのコスト削減や売上向上が見込めるか、投資対効果(ROI)を事前に試算することが大切です。また、小規模から始める「スモールスタート」や、国や自治体が提供する補助金制度の活用も有効な克服法です。
現場で使いこなせず形骸化する恐れがある
高機能なシステムを導入したにもかかわらず、現場のオペレーターが使いこなせず、結局一部の機能しか使われないという「形骸化」のリスクも存在します。多機能すぎるシステムは、かえって操作が複雑になり、現場の混乱を招くことがあります。
この問題を避けるためには、システム選定の段階から実際に利用する現場の意見を取り入れることが重要です。本当に必要な機能は何か、画面は見やすいかといった「操作性」を重視して選びましょう。また、導入後のトレーニングなど、ベンダーのサポート体制が充実しているかも必ず確認すべきポイントです。
情報漏洩などのセキュリティリスクがある
コールセンターシステムでは、顧客の氏名や連絡先といった重要な個人情報を取り扱います。特に、インターネット経由で利用するクラウド型システムの場合、情報漏洩などのセキュリティリスクを懸念する声は少なくありません。
この不安を克服するためには、システムのセキュリティ対策を厳しくチェックすることが不可欠です。具体的には、情報セキュリティの国際規格である「ISO27001(ISMS認証)」を取得しているか、データの暗号化は万全かなどを確認しましょう。また、オペレーターごとに閲覧・編集できる情報の範囲を制限する「アクセス権限設定」を適切に行うことも、重要なリスク対策となります。
コールセンターシステムを選ぶ5つのポイント
自社に最適なコールセンターシステムを選ぶためには、以下の5つのポイントを総合的に比較検討することが失敗を避ける鍵となります。
クラウド型かオンプレミス型か
初期費用を抑え、短期間で導入したいなら「クラウド型」、自社のセキュリティポリシーに合わせて自由にカスタマイズしたいなら「オンプレミス型」が適しています。近年の主流は、柔軟性と拡張性に優れたクラウド型です。
自社の課題解決に必要な機能の過不足はないか
多機能なほど良いわけではありません。「生産性を上げたい」「応対品質を改善したい」など、自社の最も重要な課題は何かを明確にし、その解決に必要な機能を洗い出す「要件定義」が不可欠です。
既存のCRM/SFAとスムーズに連携できるか
すでに社内で利用している顧客管理システム(CRM)や営業支援システム(SFA)がある場合、それらとスムーズにデータ連携できるかは非常に重要です。連携できないと、二重入力の手間が発生し、かえって非効率になります。
導入後も安心して運用できるサポートがあるか
導入時の初期設定支援はもちろん、運用開始後にトラブルが発生した際や、機能を使いこなせない場合に、どのようなサポートを受けられるかを確認しましょう。電話やメールでのサポート体制、対応時間などを事前にチェックします。
AI活用や事業拡大に対応できる拡張性はあるか
将来的にAIを活用した自動応答や音声分析を導入したい、あるいはコールセンターの規模を拡大したいといった計画がある場合、システムがそうした変化に対応できる「拡張性」を備えているかを確認することも大切です。
コールセンターの未来はAI活用が鍵に
近年、AI技術の進化により、コールセンターは単なる電話対応の窓口から、メール、チャット、SNSなど多様なチャネルを統合管理する「コンタクトセンター」へと進化を遂げています。AIチャットボットが一次対応を自動化したり、AIが通話内容をリアルタイムでテキスト化し、オペレーターにおすすめの回答を提示したりする技術も実用化されています。
これにより、オペレーターはより人間的な温かみや高度な問題解決が求められる業務に集中できるようになります。これからのコールセンターシステムは、業務効率化ツールであると同時に、顧客とのあらゆる接点から得られるデータを統合・分析し、経営戦略に活かすための重要なプラットフォームとしての役割を担っていくでしょう。
業界特有の課題を
解決できる製品を選ぼう
解決できる製品を選ぼう
コールセンタークラウドシステムが活用されている業界は幅広いため、製品選びを成功させるには、自社の業界に合った機能を備えている製品を見つけることが大切です。
当サイトでは、導入する業界別におすすめのコールセンタークラウドシステムをピックアップ。業界特有の課題をどのように解決できるのか、理由と併せて紹介しています。自社の業界にマッチする製品を見つけたい方は、ぜひチェックしてみてください。
業種別
クラウド型コールセンターシステム3選
クラウド型コールセンターシステム3選
コールセンターの運用を適正化し、事業成長を加速させられるクラウド型システム。業種・業界ごとの課題に応じて導入し、変化に強いコールセンターを構築しましょう。
金融・保険業界
Genesys Cloud CX

引用元:Genesys Cloud CX公式HP
(https://www.genesys.com/ja-jp)
(https://www.genesys.com/ja-jp)
- 強固なセキュリティ対策で
重要な顧客情報を守る - 複数の防御対策を掛け合わせ、企業ごとに固有の暗号化キーも採用。PCI DSS、GDPR、ISO 27001等、国際的な金融セキュリティ基準に準拠しています。
- セキュリティとAI活用で
顧客対応・監査の負担を削減 - AIが顧客情報を分析して適切なオペレーターをアサインし、初回解決率を向上。個別対応が重要なローン・信託相談の効率化に寄与します。
金融・保険業界向けの主要機能
- オペレーター自動振分
- 顧客対応の支援AI
- 顧客記録の自動レポート
生活インフラ業界
Bright Pattern

引用元:Bright Pattern公式HP
(https://brightpattern.cba-japan.com/)
(https://brightpattern.cba-japan.com/)
- クレームが激増する
障害発生時の対応をカバー - 東京と大阪の2つのエリアでデータ同期しながら運用可能。特定エリアでの障害・災害発生時にも利用者を待たせることなく対応できます。
- チャットボットや自動音声で
24時間365日問い合わせに対応 - 24時間365日、チャットボットや自動音声が回答をしてくれます。問い合わせ対応を止めずに済み、クレーム阻止につながります。
生活インフラ業界向けの主要機能
- 通話待ち整理券
- AIチャットボット
- IVR(自動音声応答)
EC・小売業界
Re:lation

引用元:Re:lation公式HP
(https://ingage.jp/relation/)
(https://ingage.jp/relation/)
- 多様化した問い合わせ手段を
まとめて一元管理 - メール・LINE・電話・SNSなど10種にも及ぶ窓口を統合・管理。それぞれのツールへの行き来がなくなり、対応が一画面で完結します。
- 低コストで使える
EC向けチャットを搭載 - 使うほどコスト減になるEC向けチャットで簡単な対応を高速化。(3万通を超える場合は2円/通)セール時などの一時的なアクセス増も安心です。
EC・小売業界向けの主要機能
- 通話の自動文字起こし
- 単純作業のルール自動化
- 顧客情報・アドレス帳呼出